自由学園という土台を共有しているから【2025年度南沢会 委員長特別インタビュー】

南沢会報第9号2頁では紙幅の関係で、今年度委員長の想いを表しきれなかったので、この記事で補足します。
「迷ったらやってみる」
――仕事では管理職、ご家族のことなどもある中、どうして委員長を引き受けてくださったのでしょう?

(以下姫井)
同級生に優秀な人はたくさんいるのですが、おそらく皆さん事情もあって辞退されたのだと思います。
昨年春に前年度の委員から委員長をと声をかけられたのですが、さすがにすぐに返事はできませんでした。1か月くらい悩んだかな。
決定打は、改めて依頼を受けたときです。私は2024年の5月まで名古屋勤務だったのですが、そこから東京勤務に決まり、ちょうど帰京のための新幹線の中で再度依頼の連絡を受けて、ああこれはもう引き受けるしかない、と思いました。
「迷ったらやってみる」という気持ちで生きてきたので、それもありますね。


(以下梶田)
5年以上前に、普1(中1)のときの室長クラス(高3)の方に「本部委員会に入ってくれないか」と頼まれたのですが、仕事を理由に断ったんです。
その時「いつかはそういう役割をやらなくてはいけないよ」と上級生に諭されていて、そのことが自分の中でずっと引っ掛かっていました。
今年度の委員を決める前に、20人くらいの同級生に声をかけて集まって、その時に推薦されて後に引けなくなって委員長を引き受けた、という感じでしょうか。
同級生の中には、最高学部へ行かず学園と少し距離を置いていた同級生もいて、その後、南沢会への入会を誘ったら快く応じてくれたんです。
そうしたこともあって、自分も覚悟を決めないと、と思って引き受けました。

その方が入会したときには本部委員をやってくれることになっていたの?

その時はまだそうはなっていなかったけれど、でも「50歳という年齢は確かに公私ともに忙しいけれど、この1年しか委員長クラスはないし、こういうことやりたいよね・・・」などと話していて、結果的に副委員長とキャリア支援室長を引き受けてくれた頼もしい同級生のひとりです。
連日のミーティング?!
――実際に活動を始めてみていかがですか?

思った以上に忙しいというか…(笑) これからの学年の方に不安を与えてはいけないのですが、ミーティングが割と多くて。
仕事から帰って、超短時間で夕食たべて、ミーティングという日々。


妻に「今夜のミーティングは何時? 8時? 8時半?」と聞かれる(笑)。

だいたいそのくらいの時間から開始だもんね。もちろん委員長だけではなくて、他の委員も皆さん時間をやりくりして取り組んでくださっているのですが、委員長は把握すべきことが多いというのはあるかもしれないです。
ただ、同級生がみんなそれぞれにリーダーシップや分析力など、学生の時以上に持ち味を発揮してくれています。
卒業後30年たって、みんな社会で酸いも甘いも経験して蓄積してきた力をたくさん出してくれている。すごく頼もしいです。
副委員長の中には、住まいは少し遠いのですが、会員でもあり学園の保護者でもあるという立場から距離を感じさせない形で本当にいい力を出してくれている人もいます。


LINEやSlackをはじめ、情報が追いきれないくらい送られてくることもあってあせることもある。
キャッチアップしなくてはならない、ということもあるけれど、もう少しこの辺りは整理して引き継ぎたいと思っています。
あとはAIなども適宜活用しています。
――なるほど。今年度の委員がたてたテーマにもつながりますね。

そうですね。これまで4年間は前向きな言葉が掲げられていましたが、今年度は「持続可能な」ということを意識しています。
これも決して後ろ向きなことではなくて、委員会活動も発展的に適切な形にしていきたいと思っています。

「適切」「最適化」というのは人によっても違うけれど、できるだけ多くの方が肚おちできるような形を考えていきたいですね。


紙の会報も今年度、より多くの方に興味をもって見ていただきたい、読んでいただきたいと思い、カラー化に踏み切ったけれど、それがすべての人にとって最適ではないかもしれない、ということは承知の上での改革です。
ただ、学園の資料にかかわる仕事をしている同級生から、創立から約30年、創立者がご存命だった時期の特に初期は、毎年さまざまな試みにチャレンジしていることがわかる。定型を決めてとどまるのではなく、良いと思ったことは変えていく、ということを繰り返していたことが資料からうかがえる、という話を聞いて、現在に生きる私たちも、そうした創立者の姿勢から学びたいと思ったことも、この会報の改革の背景にはあります。
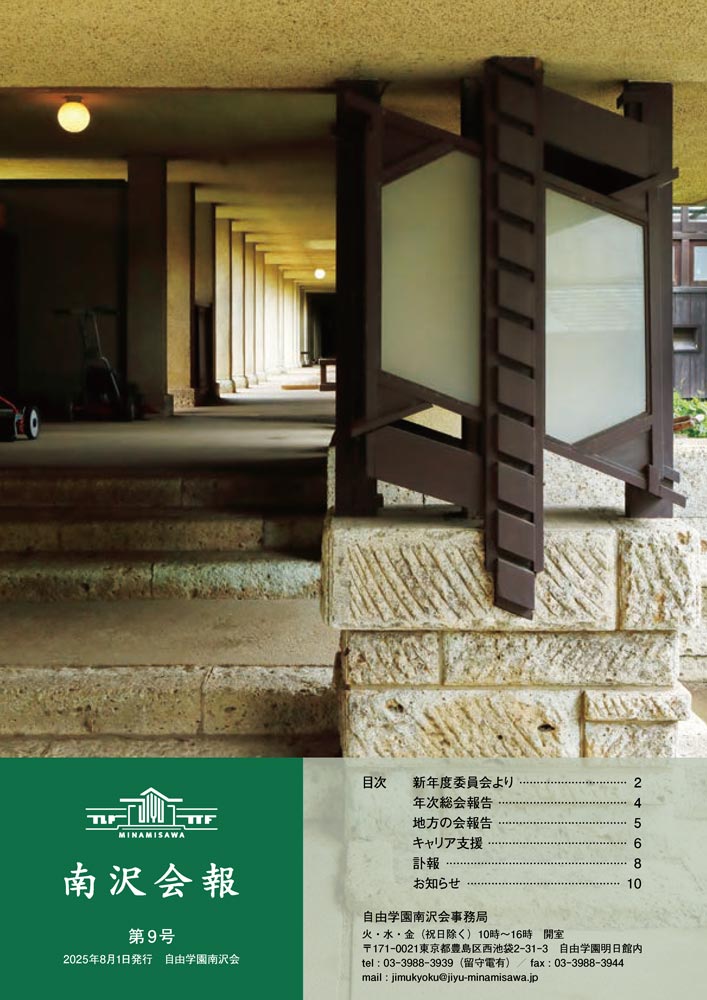

そうだね。地方の会に参加したとき、中部地方のある卒業生の方が、会報をファイリングして、暇さえあれば読み返している、とおっしゃっていた。
やっぱりそれくらい大事に思ってくださっている方がいる、ということは常に委員として自覚していたいと思いました。
世代を超えてつながれる
――地方の会が開催される際は、委員長も南沢会を代表して参加されているんですね。

そうです。これまで2か所、明日は東北の会に参加します。
どこでもとても歓迎してくださって、「(委員長の任務は)大変でしょう」とねぎらいの言葉もかけてくださる。多くの方に支えていただいていることをリアルに感じられるときとなっています。
下は20代から上は90代まで、幅広い年齢層の方が集まって交流できるのは貴重な機会ですね。


実は私たち2人はたまたま両親共に卒業生なのですが、先日北信越の会に参加したとき「自分が新入生部屋だったときの室長が君のお父さんで、新入生部屋が終わるとき室員全員に内村鑑三の本をくれたんだ」という、私が全然知らなかったエピソードを教えてくださる方もいて。
時代は違っても、同じ土台の教育を受けた者同士つながれること、その尊さを感じますね。
また北海道には「卒業生の使命は学園に生徒を送ること」とおっしゃっている方がいて。
本当に熱をもって、学園を支えることを真剣に考えている方がたくさんいる。
私たち南沢会の委員の活動もそうした方たちの想いにどうすれば応えていけるか考えないと、と姿勢を正される思いがしました。



30年以上会っていなかった人たちと
――前向きに取り組んでいけば、質も向上させつつ楽しくかかわれる委員会活動になりそうですね。最後に会員の皆様にひと言お願いします。

那須農場の支援活動にぜひいらしてください!
私も今年、この役をいただいたので参加してみたのですが、南沢会員のみならず、その家族や学園の保護者、生徒さんなど、いろいろな方と交流もできて、良い意味で「解放区」という感じがします。


「委員長はむしろ頭使う仕事に専念して」と心配して声をかけてくれるメンバーもいるのですが(笑)、なんとなく私たちは、はい、じゃあ那須の活動はよろしく、とお任せにしてしまうのも違うかな、という気持ちが強くて可能な範囲で参加しています。
結果、すごく楽しいし、いろいろな方の声も聞ける良い機会になっていますね。

本部委員会の活動は、始まってみないとよくわからない部分も多いですが、クラスメイトのそれぞれのスキルがうまく合わさって進めていけるのが魅力。
30年以上会っていなかった人と一緒に何かができるって貴重な機会ですよね。

確かに。学校が、最高学部から男女共学になり、昨年度からは中高も共生共学化されて、南沢会も5年前から男女合同の会になりましたが、同学年でいい形で委員会活動に取り組めているのではと思います。
30年ぶりの人もいれば、部が違うとほとんど「初めまして」の人もいるしね(笑)。


ほんとにそう。
だけど、それぞれ社会人経験も積んでいること、そして部が違っていたとしても、自由学園という同じ学校で教育を受けた土台があることが強みかなと。
そして、なんとなく離れていた学園のことを思い出したり、学園の現在に興味を持ったりできる貴重な機会にもなっています。
ぜひ会員の方々にも、南沢会や学園に関心を持っていただければ。そうできるよう本部委員会も知恵を絞っていきたいと思います。

そうですね。コロナ禍も落ち着いたので、ぜひ対面で皆さまとお会いできればうれしいです。
那須の支援活動や、今度10月18日にある南沢大会で会員の方々とお会いできることを楽しみにしております。
そして、私たちではまだ至らない点もたくさんあると思うので、会員の皆様の様々な思いやご意見を教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします!

2025年7月12日第5回本部委員会後、南沢会事務局にて 文責:広報室
